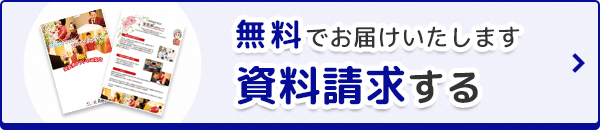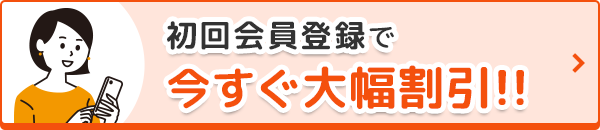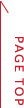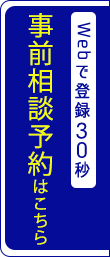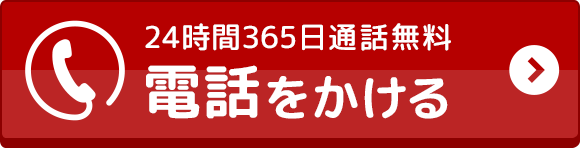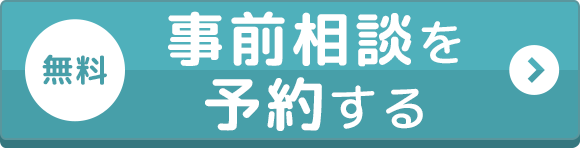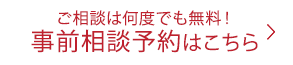【初盆(新盆)とは】時期と準備するものを分かりやすく解説
初盆(新盆)とは?意味と流れ・準備について
ご家族が亡くなられて初めて迎えるお盆を「初盆(新盆)」と呼びます。通常のお盆よりも丁寧に供養を行うことが一般的で、ご家族やご親族が故人を偲び、お迎えする大切な時間です。地域によって風習や細かな違いはありますが、日本全国で共通している考え方や準備の流れがあります。

初盆までの準備
初盆を迎えるにあたり、代表的に準備するものは以下です。
- 提灯
故人の魂が迷わず家に帰ってきていただくための灯りとされ、提灯を使用することが多いです。
花浄院では長く使っていただきたい、という想いから柄入りをご案内しております。 - お仏壇・お位牌の準備
四十九日を過ぎていれば本位牌(塗位牌)を安置します。まだ白木位牌であれば、四十九日までに準備できると安心です。 - お供えや食事の準備
故人が生前好きだった物、果物、精進料理、お団子、季節のお花などをお供えします。きゅうりの馬・なすの牛も地域問わずよく見られる風習です。 - 返礼品
親族や参列者が訪れる場合に備え、返礼品の準備をします。参列者の人数が不明な場合は、多めに用意すると安心です。 - お布施
読経や法要をお願いした際に、感謝の気持ちを込めてお寺さまへお渡しする謝礼のことを指します。 金額について迷われる場合は、「どのようにしたら失礼にあたらないでしょうか」と率直にご相談いただくことで、お寺さまも丁寧にご説明くださることがほとんどです。事前に確認しておくと、当日も安心して初盆をお迎えいただけます。 また、初盆は一年の中でも特に大切なご供養の場とされるため、一般的には通常のお盆よりも少し多めに、四十九日や一周忌など節目の法要と同程度の金額を包まれるご家庭が多いようです。表書きは「御布施」 もっとも広く使われる表書きで、迷ったらこれを選べば間違いありません。 宗派やお寺さまの考えによって異なる場合もあるため、迷ったら お寺さまに確認するのが最も安心です。
初盆当日の流れ(一般的な例)
- 迎え火
お盆の始まりに灯す火で、故人をお迎えします。
関西では8月6日の夕方に行うことが一般的です。 - お寺様による読経(法要)
初盆では僧侶に来ていただき読経をお願いすることが一般的です。ご自宅だけでなく、法要会館・寺院で行うケースも増えています。 - お焼香・献花
参列者が順にご焼香し、故人に手を合わせます。 - 会食または茶話会(任意)
参列者で故人の思い出を語り合う時間として設けるご家庭もあります。 - 送り火
お盆の終わりに灯す火で、故人を見送る習わしです。
関西では8月15日の夕方に行うことが一般的です。
まとめ
初盆は、「故人を忘れず想い続ける心」を形にする大切な供養です。形式にとらわれすぎず、ご家族が無理なく、心穏やかに迎えられることが何よりも大切です。
不安なことや準備に迷う場合は、お寺や葬儀社に相談すると安心です。
ご相談は店頭・ご自宅訪問・お電話などで行っております。スタッフが詳しくご説明します。
ご来店での相談は毎日 10時~16時の時間帯で随時受け付けております。
ご予約はお電話または事前相談フォームからお気軽にお申し込みください。
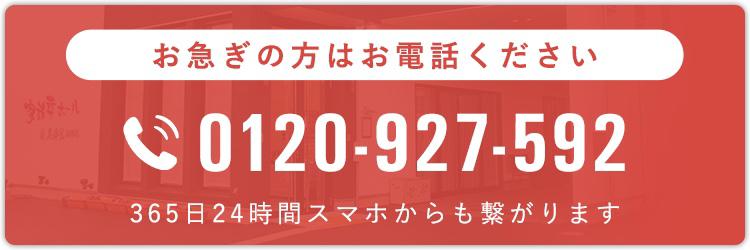
お電話は24時間365日対応しております。
なかなか会館に足を運ぶ時間はない、という方でも、24時間都合の良いタイミングで質問することが可能です。
2024年05月08日